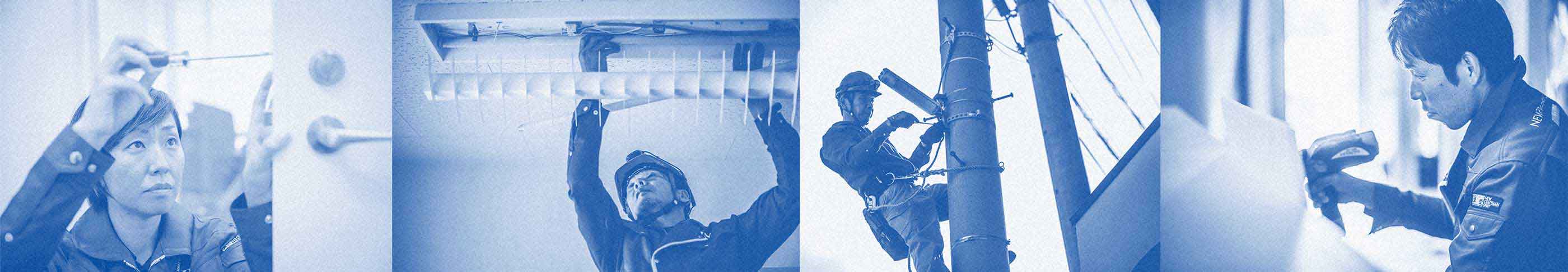INTERVIEW代表インタビュー
解決したい社会課題
大切な建物の予防保全をお客様自身が行う世の中へ
JMでは現在どのような社会課題の解決を目指していますか?
大きく二つあります。まずはバブル経済期に作られた大量の建物が、約30年経って一斉に寿命の折り返し地点を迎えています。
建物はどんどん劣化していくので、60年の寿命を90年に延ばすため、早めに予防保全を行うことが必要です。建物を健康な状態に保つことは修繕のためのコスト軽減にもつながります。
もう一つは、少子高齢化が進み、建物のメンテナンスを行う職人が激減していること。
直す人間がいなくては壊れた建物がそのままになってしまうし、経済の循環にも支障が生じます。そのため職人を増やすことは急務です。
なぜそうした課題に着目しているのですか?
残念ながら建設業というのはあまり好かれていません。
この産業がなければ世の中は困るはずなのに、社会的な評価は低い。その背景にあるのは、建物を作ることには力を入れるのに、使い始めてからは放ってしまう傾向です。使い始めてからは、使い勝手に関するクレームがくることが多いので、多くの建設会社は建物が出来た後はタッチしたくないのです。そのうえ修繕を行う職人の待遇は良いとは言えず、成り手は減る一方。これではサービスの質も上がりません。
しかし、私自身は建設業が大好きで、「大事な産業」とみなさんに思ってほしいのです。そして、こうした“維持管理を担う職人のなり手が減っている”という社会課題を解決することで建設業を改めて認めてもらいたいという想いから当社のビジネスを立ち上げたのです。
JMが新築は一切やらずに既存の建物の点検と修繕に注力しているのは、建物は維持管理が何より大事であり、その領域で働く人たちを「ニュークラフトマンスピリット」というキーワードのもと誇り高い職人にしたいという気持ちがあります。
ビジネスモデルのきっかけを教えてください。
前田建設のダムエンジニアだった約40年前の私は、山奥の直径10kmに広がる現場の中で、作業員3,800人を管理する技術者40名の一員としてダム建設の仕事をしていました。
当時、朝礼が終了すると3,800人の作業員は山の中の約150か所に分散して作業に当たっていたので、技術者40人が分散して150か所の現場監督を行っていました。その際、今のようにスマートフォンはなく、技術者40人はトランシーバーを持って作業の状況を音声のみで確認しあう時代でした。リアルタイムな管理が出来ず、作業場から作業場へと山の中を歩き回る、無駄な時間が多い毎日でした。150の現場を回って、現場詰め所に集まり、全体3,800人の作業状態を一元化していました。
私は若かったので、重くて高い測量器具等を持って作業の準備をしたり、普通のカメラで進捗状況を写真撮影し、カメラ屋さんに頼んで数日後に仕上がった写真を紙に貼り付けて写真報告書を作成するなど、無駄で生産性の悪い仕事のやり方を改善しようと考え、当時フィルム事業を行っていた数社に相談していましたが、当時改善することは出来ませんでした。
この考え方が、25年前のJM創業の基本となりました。全国北海道から沖縄までを、当時の直径10kmのダム現場と同様に、直接現場は見えなくても、写真と報告がリアルタイムに出来、その場で点検等の報告書が作成できるシステムを導入し、衛星通信で東京に一元化出来ないかと考えた結果が、今のJMのビジネスモデルに繋がっています。
そのビジネスモデルが、先ほどの社会課題の解決にどのようにつながりましたか?
20年以上前から取り組んできたおかげで、コールセンターシステムにしても、決裁承認システムにしても、当社はいち早くデジタル化を進めることができました。
予防保全についても、過去に蓄えた豊富なデータから「こうした状況ではこういうトラブルが生じる」という対処法を引き出すことができるので、お客様がスマートフォンで撮影した画像を
AI
によって解析し、トラブル発生の確率や「こうすればお客様自身でも対処できます」という修繕方法を提示するといったことも行っています。
そのため、維持管理の職人の業務効率化が進み収入が高まるので、ニュークラフトマン(ITを活用する職人)を目指して入職する職人が増えています。

お客様が自分で修繕したら JM の売上が下がるのでは?
ITの進化により、お客様が自分で修繕する時代が来るでしょう。
しかし実際には、お客様自身で全て修繕できるわけではありません。
料理番組を見て自分で作ることがあっても、料理への意識が高まるほど、本物を求めてレストランへ行きますよね。それと同じで、自分で建物を修繕しようとすれば予防保全の意識が高まり、上手く直せなかったらプロの職人に依頼します。
つまり、建物の維持管理への関心、もっと言えば大切な資産への関心が高まるのです。
そうなれば当社の売上が下がることにはつながらないという考え方です。
フランチャイズ制度の導入によってどのような成果がもたらされましたか?
当社はJM100%のフランチャイズ制度を採用しています。つまり、当社以外の仕事はしないFC会社が全国にあり、1社1社が自立して自分たちの地域の仕事に対応する構図となっています。
ここ数年はコロナウイルスの影響により地方の経済が冷え込み、厳しい状況に陥っている工務店が多かったですが、当社のシステムを活用することで効率化が図れ、売上は下がっても利益は伸びている FC会社は少なくありません。地域の中で仕事が回せるということは、地方の経済循環にも貢献できていると言えます。たくさんの FC会社から感謝の言葉も頂いていますが、それが最大の成果です。
今後のビジョンを教えてください。
地方自治体の財政は厳しく、おそらく今後はそれに拍車がかかっていくと予想されます。
そうした中で、健康志向で人間の寿命が伸びているように、建物の長寿命化を志向する時代になってきたように思います。
実際に、建物点検をしっかり行い、5年先、10年先の修繕費用を算定してほしいという依頼が増えています。
まさに予防保全ですね。
当社のビジョンは、豊富に蓄えたデータから予防保全のお手伝いをすること。 それができれば資産価値の持続可能性を高めることができ、地方の経済、延いては 日本経済の成長に貢献できると考えています。

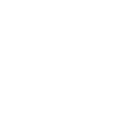 お問い合わせ
お問い合わせ